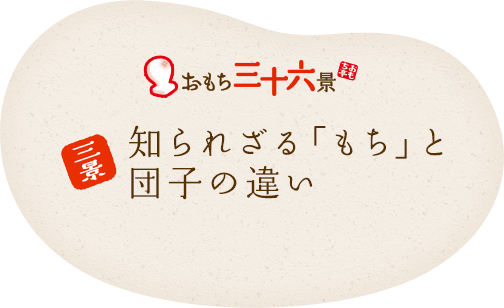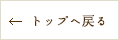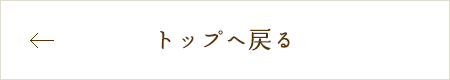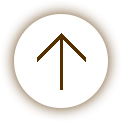9月8日は中秋の名月、十五夜のお月見です。大陸から月を眺めて楽しむ上流貴族の宴として伝わったお月見は、次第に農作物の収穫を感謝して月見団子をお供えする、日本独自の風習へ変化していきました。お餅の「もち」の語源には、満月(望月)の「もち」という説がありますが、お月見のお供え物はもちではなく団子なのはなぜでしょう?実は、もちはお祝いごと、団子はお供え物に使われると決まっているのだそうです。
「そもそも、おもちとお団子ってどう違うの?」そんな素朴な疑問を抱いた方もいるのではないでしょうか。なんとなく食べているおもちとお団子、似ているようでその違いはナゾ……。どちらも原料はお米ですが、つくり方に違いがあるようです。
ご存知のように、おもちは蒸したもち米を、臼と杵で粘り気が出るまでついてつくります。一方、お団子はうるち米を粉に加工した「上新粉(米粉)」にお湯を加えながらこね、丸めたものを蒸して加熱します。
「蒸して」から「つく」のがおもち、「こねて」から「蒸す」のがお団子。もっとおもちに近いモチモチ食感のお団子を楽しみたいなら、うるち米と餅米をブレンドの「だんご粉」がおすすめです。
一口に「お米からつくられる食べ物」といってもさまざまな種類の粉があり、食感を変えるためのつくり方も工夫されているのですね。
意外と知らない「おもち」と「お団子」の違い。誰かとおもちを食べるときに話が弾むこと間違いなしの「豆知識」です。
文・松浦松子
【参照URL】
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%A3%E5%AD%90
http://www.kinouchi.jp/komeko.html