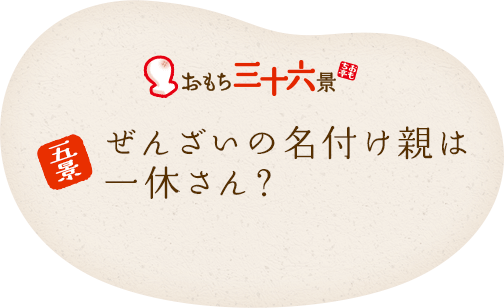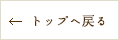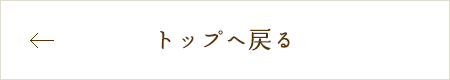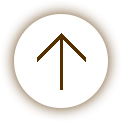あんことおもちが絶妙に絡み合い、ほっこりとする甘味「ぜんざい」。その「ぜんざい」を日本ではじめて食べたのは、とんちで有名な一休さんだと言われています。
「善哉(ぜんさい)」という漢字は「よきかな」とも読むことができます。「よきかな」は仏教用語で「すばらしい」を意味するサンスクリット語の訳で、仏様が弟子を賛成・称賛するときに使う言葉。一休さんがはじめて口にした「ぜんさい」のあまりのおいしさに、「善哉此汁!(よきかなこのしる)」と叫んだことが語源と言われています。「善哉(ぜんざい)」という名前には、「ブラボー!」や「エクセレント!」といったおいしさへの驚きと感動がつまっているのですね。(出雲大社の「神在(じんざい)祭」で振る舞われた「神在餅」が発祥という説もあります)
また、「ぜんざい」は地方によって指すものが違うこともあります。関東では、お汁粉に比べて汁気のないものを表しますが、関西では「つぶしたあんこでつくったお汁粉」のこと。こしあんでつくられたものはそのまま「お汁粉」と呼ばれます。汁気の少ない関東の「ぜんざい」は、関西だと「亀山」に当たります。
沖縄で親しまれている「ぜんざい」は、なんと甘く煮た金時豆がかかったかき氷!温かい「ぜんざい」を頼んだつもりが、冷たいかき氷だった……なんて驚かないように、気をつけてくださいね。
文・松浦松子
【参照URL】
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%9C%E3%82%93%E3%81%96%E3%81%84
http://gogen-allguide.com/se/zenzai.html
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/126231/m0u/