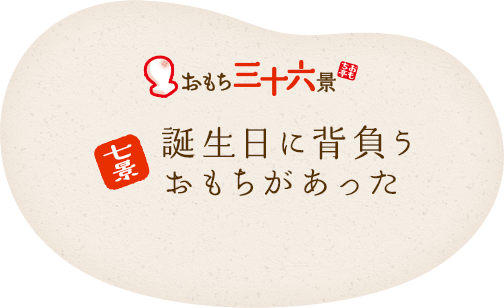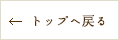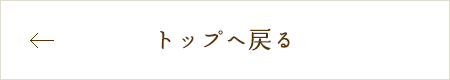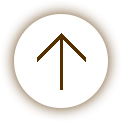一升餅って知っていますか? これは、一升(約2kg)のもち米から作られた丸餅のこと。日本では昔から、子どもが一歳の誕生日を迎えると、お祝いとして一升餅を用いたそうです。
さて、この一升餅。なぜ一升なのでしょうか。じつは、一升という言葉には、大切な意味が込められていました。埼玉県で代々餅菓子屋を営み、石臼と杵で毎日つきたてのおもちをつくる「栄屋菓子舗」にその由縁と一升餅でのお祝い方法について聞いてみました。
一升餅の一升は"人の一生"という言葉になぞらえており、「一生健やかに育つように」などの願いが込められているそうです。
お祝い方法はいたって明快です。一升餅を風呂敷に包み、ヨチヨチ歩きの子どもに、たすきがけに背負わせます。もちが重いので、小さい子どもは、後ろに重心をもっていかれて転んでしまいがち。そこに「丸い良き人生を、しっかりと大地を踏んで歩めますように」との願いが込められているんだとか!
一方、ハイハイをしている子どもには、両足を良く拭いてからおもちを踏ませてあげるといいそうです。もち踏みは「丈夫な足になるように、一生(一升)食べ物に困らないように」という意味があるそうですよ。
お祝いが終わったら、みんなで一升餅を分けて食べます。昔から、なるべく多くの人で分けあって「たくさんの愛がこの子に注がれる様に」と願ったそう。
尚、栄屋菓子舗さんによると、これらは東京や埼玉などで引き継がれる江戸流の方法だとか。地域によって、一升餅の呼び名も「しょい餅」「餅踏み」「誕生餅」「一歳餅」など様々で、お祝い方法も違うということでした。どんなお祝い方法があるのか、調べてみるのも奥が深くて面白そうです。
バースデーパーティにクリスマス、バレンタインデーなど、西洋から入ってきたお祝い行事も楽しいですが、失われつつある日本の伝統的な家庭行事、大切にしていきたいですね。
文・米田ロコ
取材協力:栄屋菓子舗 048-771-1222