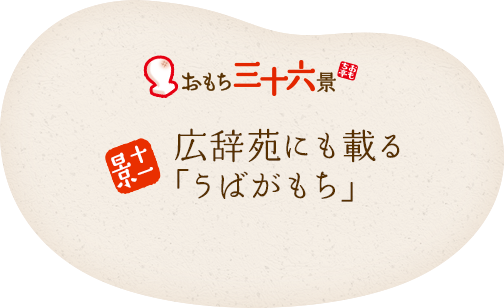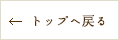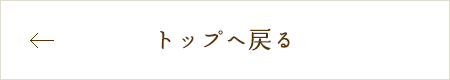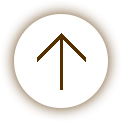徳川家康も、松尾芭蕉も食べ、歌川広重が描き、与謝蕪村が歌に詠んだというもちをご存知でしょうか? 現代でいえばセレブ御用達ともいえるそんなおもちが「うばがもち」です。しかもこの「うばがもち」は、ある感動のストーリーとともに、市井の人々から人気に火がついたといい、現在では広辞苑にも載っているほどなのです。はたしてその感動のストーリーとは?
時は永禄十二年、近江(現在の滋賀)の大名である「佐々木左京太夫義賢(ささきさきょうだゆうよしかた)」が織田信長に滅ぼされました。義賢が三歳になる曾孫を乳母「福井との」に預けたのが、この物語のはじまりです。「との」はふるさとの草津(滋賀県)に戻り、幼子を育てることにしました。しかし「との」には子供を育てるのに十分なお金がありません。そこで「との」はもちを作って街道で売ることにしたのです。
街道を行き交う人々は、そんな「との」を不憫に思い、もちを買って行ったといいます。幼子を育てるためにもちを売る姿、そして実際にそのもちの味自体も評判を呼び、いつしか「乳母がつくるもち」として「うばがもち」と呼ばれるようになったのです。
それから年月は過ぎ、慶長年間(1596~1614)、関ヶ原の戦いで徳川軍が勝利した頃のことです。当時「との」は84歳となっていましたが健在でした。「うばがもち」の噂を聞いた家康は「との」を呼び、「うばがもち」を献上させました。そこで家康は「との」の誠実な生き方を称え、褒美を授けたのです。
以来、江戸時代の文化人たちは我先にと「うばがもち」を賞味したり、作品の題材に取り上げたりするようになり、「うばがもち」の名は全国に広がりました。その中には、かの松尾芭蕉や与謝蕪村、歌川広重がいました。
現代において「うばがもち」を製造・販売している「うばがもちや」の片岡英三さんによると「かつての「うばがもち」には、『上製』と『下製』という2種類があり、上製は本陣等で有力者の方々に差し上げられ、下製は一般の方々が買われていたと言われています」とのことですが、現在は1種類。また数年前までは他県のお米を使っていましたが、現在では減農薬栽培による地元の農家の高級もち米を使うようになったといいます。
「うばがもち」の感動のストーリーに思いを馳せながら、当時の文化人たちも食べられなかったであろう、現代の技術による味を味わう。そんな贅沢な気分に、小さな「うばがもち」一つで浸れる…。なんとも良い時代なのかもしれません。
文・照沼健太