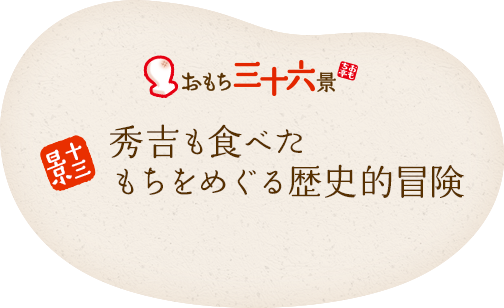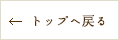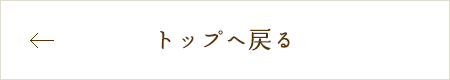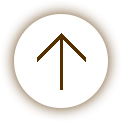伊勢神宮のお膝元、たくさんの観光客で賑わう門前町の一等地に、かの豊臣秀吉が参拝の際に茶屋でもちを焼いて食べ、「美味也と御称美なし故太閤餅と号けし云々」と言ったとされる「太閤出世餅」があります。450年前から伊勢神宮参拝客に愛されてきたというこの銘菓には、歴史をめぐるドラマがありました。
優しく、柔らかく、それと同時にピンと張った雰囲気のある伊勢神宮は、近年パワースポットとしても人気で、いつも観光客で賑わっています。そんな伊勢神宮とセットで参拝客の楽しみになっているのが、三重の食材を使った飲食店や、土産物屋が立ち並ぶ門前町の散策。松阪牛や海鮮を楽しんだ後に、ぜひ立ち寄りたいのが、450年の歴史を持つといわれる「太閤出世餅」を販売する、「有限会社太閤餅」です。
門前町の中でも伊勢神宮に最も近い内宮宇治橋前に位置している「太閤餅」。お店に伺うと、社長の河口妙さんがあたたかい笑顔で出迎えてくれました。店内には、河口さんの旦那さんが法人化した際に仲間からもらったという、秀吉の旗印でもあったひょうたんがたくさんぶらさげられ、名前の由来にもなった秀吉の足跡が感じられるよう。
しかし何百年もの歴史ある地名が往々にしてそうであるように、「太閤出世餅」がなぜそう呼ばれるようになったのかは諸説あり、最近まではっきりとした由来が示されていませんでした。そのことで「太閤餅」に嫁いだ河口さんは悩んだこともあるといいます。
「ある日、酔っぱらいの方がお店に来て『なんで伊勢で秀吉なんだ!デタラメじゃないか!』とすごまれてしまったんです」と話す河口さんですが、ご自身もその由来には疑問を抱いていたそうで、それを機に伊勢の歴史の本を読み漁るようになったといいます。「ご贔屓にしていただいていた東京の大学の先生からたくさん本をいただき、図書館にも通いながら2年かけて『太閤出世餅』の歴史を知るために勉強をしました」
そうして発見したのが、江戸時代後期に伊勢神宮の神主が当時の文化や人々の生活を記した古文書「神都長嶺記(しんとながみねき)」にあった「秀吉公御光臨の時献ぜしに、珎美味也と御称美なし故太閤餅と号けし云々」という一節だったと言い、今ではお店のパンフレットだけでなく、県の観光ガイドにもそう記されるようになりました。
「本をいただいた先生に、私が調べて書いた文章を見せたら『歴史なんて本当のところは絶対に分からない。だから、これはあなたの“学説”として自信を持っていい』と言っていただいたんです」と河口さんは笑顔を見せてくれました。
一つ一つを鉄板で手焼きすることでおもちと小豆の風味を引き出し、保存料等の薬剤は一切使用していないという「太閤出世餅」は、おいしさを保つため、脱酸素剤とともに個包装し、伊勢志摩地方以外では原則的に販売していないそうです。その素朴であたたかな味わいは、おもちそのものだけでなく、おもちを取り巻く歴史にも真正面から取り組む、河口さんの堅実な姿勢のあらわれのように感じられました。
文・照沼健太