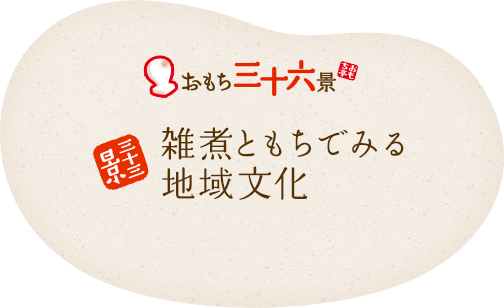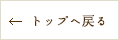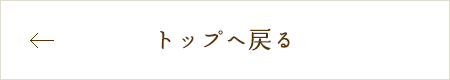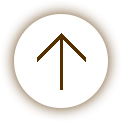正月といえばお雑煮です。年神にもちとその土地の産物を供え、一つの鍋で煮て神と共に味わうのが雑煮の起源。それだけに、地域性が強く表れるのが面白いところです。
正月に雑煮を食べる風習が庶民に根づいたのは、元禄時代以降といわれます。発祥の地は、貴族文化が息づく京都。丸めたもちを白みそ仕立てにするのが習わしで、京都の影響が色濃い西日本では丸もちがスタンダードです。
いっぽう武家文化の江戸では、のしもちを切った角もちが普及。「敵をのす」という語呂が好まれたのと、狭い長屋住まいのため、もち屋のもちを買う町人が多かったのが理由とか。もちを丸めるのは手間なので、まとめてついたもちを一気にのし、それを各家で四角く切って食べていたのです。この風習が東日本に広まったため、東は角もち、西は丸もちという傾向ができたようです。
文化の差は、汁にも表れます。京都を中心に近畿の一部、福井県や滋賀県はみそ仕立て。武家(大名)が支配した土地では、「めでたさにみそがつく」からと、すまし汁仕立てに。変わり種は、出雲地方の小豆汁仕立て。塩味のすまし汁にもちを入れ、煮小豆をのせて、砂糖をかけて食します。
甘いといえば、香川県のあんこ入り丸もちも個性的です。四国讃岐は砂糖の名産地。高価な砂糖をお正月くらいは贅沢に食べようと、あんこにしてもちでくるんだのが始まりとか。
もち以外の具も、山あいでは山の幸、海沿いなら海の幸と、バリエーションは無限大!ふぐを入れる広島県や、もちに別皿のきな粉をまぶしつつ食べる奈良県の雑煮もおいしそう。一体どんな味なのか、想像がふくらみますね。
文・田邉愛理
参考:『全国から集めた伝統の味 お雑煮100選』編著:文化庁 出版:女子栄養大学出版部 『聞き書 ふるさとの家庭料理 ⑤もち 雑煮』解説:奥村 彪生 編著/出版:農山漁村文化協会