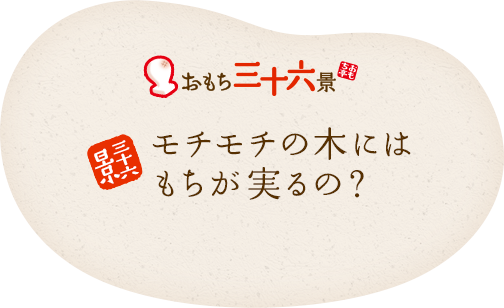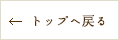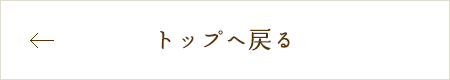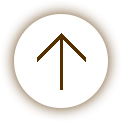弱虫の豆太が大活躍する名作絵本『モチモチの木』。秋になる茶色い実を粉にして、「もちにこねあげて、ふかしてたべると、ホッペタがおっこちるほどうまいんだ」……という一節に、「どんな味なんだろう!」とワクワクした人も多いことでしょう。
この「モチモチの木」、子ども時代の筆者はドラえもんの「パンの木」みたいな木をイメージしていましたが、じつは「栃(とち)」という日本特有の樹木。その実は、縄文時代の昔から食用にされてきました。
本にも「デッカイデッカイ木だ」という描写があるとおり、栃の木は成長すると、大きいものは高さ30メートル、幹の径2メートルほどの大木になります。実は栗に似ていますが、アクが強くそのままではとても食べられません。アク抜きは、水にさらして天日に干し、ゆでて皮をむいて水につけ、さらに広葉樹の灰で煮て……と、およそ半月から1ヵ月ほどもかかる大変な作業。しかし、もち米と一緒について「栃もち」にすると、苦みと渋みが風味に変わり、絶品のおもちになるのです。
大木に育つため、一本の木からたくさんの実を拾える栃の木。アクが強いので虫がつきにくく、動物に食べられることも少ないといいます。そのため、飢饉のときには非常食になり、多くの人の命を救ったのだとか。なんだか、病気のじさまを助けようと勇気を奮い起こした豆太の、たくましく成長した姿のようですね。
文・田邉愛理
参考:『モチモチの木』作:斎藤 隆介/絵:滝平 二郎 岩崎書店|『日本民俗大事典』吉川弘文館|『日本国語大辞典 第二版』小学館|栃餅に寄せて 堀井 光子